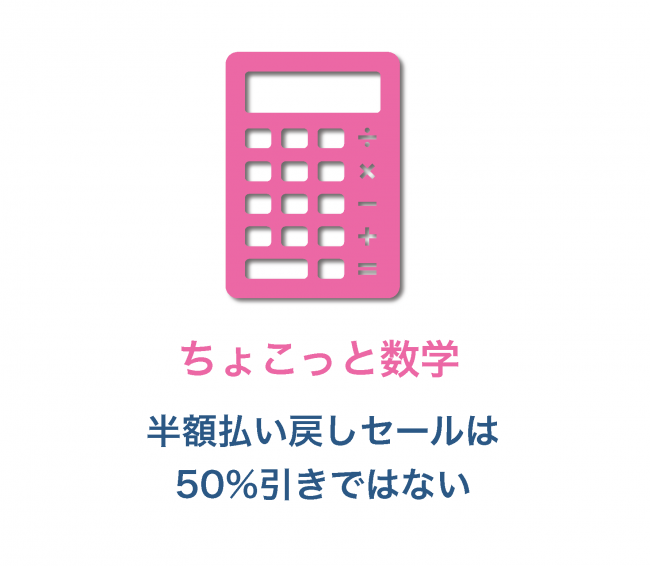独学コーチ長宮慶次です。 あなたは今、勉強していますか?
学校の勉強を頑張っている中学生や高校生、受験のために必死に勉強している予備校生、資格やスキルを得るために働きながら勉強している社会人など、勉強している人はたくさんいると思います。そして、思うように勉強が進まず悩んでいる人も。
そんなあなたのために、少しでも力になれれば、と思って記事を書いています。
「やる気が出ない」の裏にある心理
「勉強しなきゃいけないのはわかっているんですけど、やる気が出ないんですよ」という受験生、 「うちの子はやる気が出れば伸びるんです。先生、やる気を引き出してくれませんか?」という保護者からの要望は、学校の先生や塾・予備校の講師であれば、毎年のように受ける相談です。
もちろん私はプロですから、何とかして要望に応えようと様々な方法を使って生徒のやる気を引き出します。
しかし、今日はその方法についてお伝えする前に、「やる気が出ない」の裏にある人間の心理についてお話ししたいと思います。

「やる気が出た」けれど・・・続かない
「やる気が出ない」の反対の意味、つまり「やる気が出る」というとき、どんなイメージを持ちますか?
何かこう、内側からじわじわと湧き上がってくる、もしくはメラメラと燃え上がってくるイメージでしょうか。
確かにそれは、私にも実感があります。
そんなときは勉強も仕事もはかどりますし、多少のことは苦になりません。毎日常にこの状態であればどんなにいいか。
しかしそんな状態は常に続くことはありません。
燃え盛っていた焚火もいつしか消えてしまうように、内側から湧き上がっていた「やる気」も嘘のように静まり、平静な状態になります。
それどころか、「何かやる気出ないんだよなあ」と、仕事中も上の空になったり、問題を解いても計算ミスばかりしたり。
あなたも、そんな経験はあるでしょう?
そこで普通の人は「やる気が出ない」状態を「やる気が出ている」状態に変える方法はないか、と考えることになります。最初に紹介した受験生と保護者の相談は、まさにそれです。でも、そう考えることは正しい道でしょうか?
私はその思考を変えるべきだと思っています。

「やる気が出ない」という言葉が隠している「やりたくない」という気持ち
そもそも「やる気が出ない」という言葉は、正しい言葉だと思いますか?
正しいも正しくないも、本当のことだからしょうがない、そういう人は多いと思います。
でも、私はそうは考えません。
「やる気が出ない」という言葉は、自然に出てくるはずのものが出てこない、そしてそれは自分の責任ではない、という意味に聞こえませんか?
人間とは弱いものです。私も含めてみんな、この「やる気が出ない」という言葉を使うことで、自分の本当の気持ちを隠し、自分の責任を回避しているのではないでしょうか。
その本当の気持ちとは何か。
それは「やりたくない」です。
そう、「やる気が出ない」の本当の意味は「やりたくない」なのです。
まずは、自分が「やりたくない」と思っていることを認めましょう。「やる気が出てこない」などと、まるで第三者が自然現象について語っているような言葉を使うのは止めましょう。
そうしないと、「やる気」が出ないのは自分の問題ではなく、「やる気」を他者から与えてもらおうとする心理が働いてしまいます。そして、やる気が出ないことを他者のせいにし、また「やる気」を与えてくれる他者を探す、という悪循環にはまってしまいます。
ですから、まずは「やる気が出ない」という言葉を使わず、「やりたくない」と口にするようにしましょう。

やりたくなければやらないのか
では、「やる気が出ない」は「やりたくない」という心理であることを自覚したとして、それをどう解決すればいいのでしょうか。
結局、勉強ができないことに悩んでいるわけですから、「自分はやりたくないんだなあ」と自覚しただけでは問題は解決しません。
「やりたくない」を「やりたい」に変える方法はあるのでしょうか?
そう思う人もいるでしょう。その不安はよくわかります。その不安への対応策についてお話しいたします。
では冒頭で紹介した受験生と保護者の相談を、もう一度見てみましょう。
- 「勉強しなきゃいけないのはわかっているんですけど、やる気が出ないんですよ」
- 「うちの子はやる気が出れば伸びるんです。先生、やる気を引き出してくれませんか?」
これ、わかりますよね。本当の意味はこうなります。
- 「勉強しなきゃいけないのはわかっているんですけど、やりたくないんですよ」
- 「うちの子はやりたい!となれば伸びるんです。先生、やりたい!という気にさせてくれませんか?」
この考えの持ち主は、無意識のうちに次のような前提条件を受け入れていることになります。その前提条件とは、
「やる気が出なければ勉強しなくても仕方がない」
つまり、
「やりたくなければしなくてもいい」
です。違いますか? だって、勉強が出来ていないので「どうすればやる気が出ますか(どうすればやりたい!となりますか)」と相談しているのですよ?
私は、この前提条件が間違っていると思うのです。
不安定な「気持ち」に左右されない仕組みを作る
やりたいとかやりたくないという気持ちは、毎日刻々と揺れ動くものです。前述のように、やる気が燃え上がっているときもあれば、そうでないときもあります。
大切なことは、そんな不安定な気持ちに左右されずに、着々と勉強を進めていく仕組みを作ることなのです。
あなたは朝、歯を磨いていますよね?顔を洗っていますよね?
歯を磨く前、顔を洗う前に「今日は磨きたくないなあ」「洗いたいくないなあ、今日はやめとこう」などと考えますか?
そんなこと考えもせずに、歯を磨き、顔を洗っているでしょう。
勉強も同じようにすればいいのです。
決められたタイミングになったら、やりたいとかやりたくないとか考える前に「やる」のです。
そうすることで、勉強は淡々と進めていくことができます。
「やりたくない」を「やりたい」に変えることよりも、気持ちに左右されない勉強する仕組みを作ることが大切なのです。

詳細に計画し、何も考えずに勉強を始めよう
具体的には、ある時刻になったらこの問題集を2ページやる、などと決めることです。できれば、詳しく決めておいた方がいいでしょう。 どの科目をするのか、どのページをするのか、どの机でするのか、何時までするのか、・・・などなど。
勉強を始める時間だけしか決めていないと、その時刻になってから「さあ何をしようか」と考えることになります。
すると人間はすぐに「したくないなあ」という気持ちになってしまいます。
勉強を始める前に考える場面は極力減らし、勉強の内容についてだけ頭を使うようにするのがコツです。

この記事のまとめ
いかがでしたか? 「やる気が出ない」と悩むあなたへ伝えておきたいこと、それは
- 「やる気が出ない」は「やりたくない」の意味
- やる気のあるなしに左右されずに勉強する仕組みをつくろう
もちろん、私個人の経験に基づく意見ですので、万人に当てはまるかどうかはわかりません。 でもきっと、役に立つ人もいると思います。そんな方はぜひ参考にしてください。
今日の格言・名言

- 言葉というものは、人の心を映しもすれば隠しもする
- やりたければやれ。やりたくなくてもやれ!